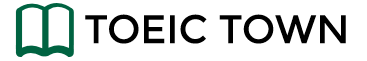あなたはemployer(エンプロイヤー)とrecruiter(リクルーター)の違いを説明できますか?
employerもrecruiterも人を雇う立場の人間であるという意味では同じですが、その役割は全く異なることを理解する必要があります。
”リクルーター”という単語は日本語でも頻繁に使われるので、イメージができる人も多いと思いますが、employerという単語は聞き慣れない方も多いことでしょう。
そこで今回はemployerとrecruiterの違いを詳しくご紹介します。
Recruiterの意味

まずrecruiterです。
recruiterはもともと軍隊において新兵を募集する人という意味でしたが、現在の一般的な使い方ではリクルートをする人、つまり採用担当者という意味です。
企業の人事部の中で求人広告を出したり書類審査や面接を行う人間や、ヘッドハンティングをする人間のことです。recruiterの仕事内容には募集を出すという作業も含まれており、例え誰も応募してこなかったり、最終的に誰のことも雇わなかったとしても、募集をかけている時点でその人はrecruiterです。
また、リクルーティングを専門にしている企業に採用を委託する場合は、このリクルーティング会社もrecruiterとなります。例えば、小規模な企業が内部に採用担当人事を持っておらず、リクルーティング斡旋企業に頼んで人材を探してもらう場合です。
Employerの意味

次にemployerです。
employerは雇用主や使用者という意味です。つまり、社長や代表取締役、個人事業主など、給料を支払って誰かを雇う/使う立場にある人間は全員employerです。
普段の会話の中で例えば「I want to become an employer rather than an employee.」というように使われた場合は、「私は雇われるよりも、人を雇う立場になりたい」という意味になります。
また、人でなくとも、雇用主の企業自体をemployerと呼ぶこともあります。
例えばソフトバンクの社長は孫正義さんですが、ソフトバンクの従業員にとって、employerはソフトバンク社自身とも言えるということです。
雇用契約書や雇用証明書類などには、代表取締役などの個人名ではなく社名がemployerとして書かれていることがほとんどです。
EmployerとRecruiterの違い

通常の場合、employerは雇用主というだけで、採用する人間というわけではありません。しかし、employerとrecruiterが同じ人間という場合もあります。中小企業の社長や個人事業主が直々に募集や採用に携わっている場合です。この場合、社長や個人事業主である人間は必ずemployer、つまり雇用主であり、彼らは採用も行っているのでemployer = recruiterとなります。
また、recruiterは例え誰も採用しなかったとしても、採用するための作業を行っているだけでその人はrecruiterだと呼べますが、employerの場合、誰のことも雇用していない人間はemployerとは呼べません。
最後に、経営者の雇用状態はしばしば、self-employedという単語で表現されます。selfとは自分自身という意味で、self-employedとは自分の会社で給料をもらいながら自分自身を雇っている状態ということになります。
一方でself-recruitedという単語は存在しません。なぜなら、自分の会社で自分を雇うことはできても、自分自身が同時に採用者と応募者にはなれないからです。
まとめ

ご理解いただけたでしょうか?
人を雇う人間という意味では同じですが、employerとrecruiterにはそれぞれ違った役割があります。
人事部での仕事や雇用のための法的書類などでは、employerという単語は非常に頻繁に使われます。ですので、二つの違いをしっかりと理解した上で、正しい英語を使えるようにしましょう。
担当ライター:エレン (日本の高校を卒業後、レイクランド大学ジャパンキャンパスにて準学士号を取得し英語力を向上、その後アメリカのペンシルバニア州立大学にて教育政策学で学士号を取得。留学中から交際を続けていたアメリカ人男性と大学卒業後に国際結婚し、現在はニューヨーク在住。)