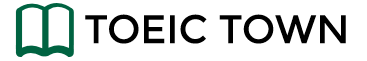2010年に英語の社内公用語化を打ち出した楽天。
発表当時、英語公用語化については各所で賛否両論を呼び、さらには英語公用語化後で業務に支障を来たしているという社員の声が聞こえるなど、正直、冷ややかな受け止め方をサれていた方が多いのではないでしょうか?
例えば、会議中に重要な話題となると、1回英語で言った後に、「ここは大事な点なので、日本語で言います」と言ってフォローしないとならず、一時、社内流行語が『大事な点なので日本語で話します』になっていたとか(笑)
そんな楽天の今について三木谷社長が語ってくれた記事がありましたので紹介します。
――(英語公用語化導入について)今、どうですか。振り返ってみて。
いや、もうこれは、ヤバイですね。
――どうヤバイですか?
いや、もうこれがなかったら、たぶん今の地位にはいないと思います。売り上げもどんどん伸びていますし、国際的なプレゼンスも上がってきていますし、入社する社員のクオリティも非常に上がってきています。社員の視野もまったく変わってきている。
いくつか事例を挙げると、ひとつ目はエンジニアの採用。現在、日本のエンジニアの採用の70%は外国人です。
日本でコンピュータサイエンスを専攻している卒業生は、だいたい年間2万人しかいません。それに対し、アメリカは約6万人、中国は100万人、インドは200万人いるんですよ。だから何百万人のプールから人を雇うのか、それとも2万人のプールから雇うのかによって、競争優位が全然変わってきます。
2つ目の事例として、日本で築いてきたビジネスのノウハウを、海外に浸透させていく流れが出てきました。今までは「日本」と「国際」の2つに担当を分けていましたが、今年からこれを一緒にしました。つまり日本の楽天市場のトップが、海外のeコマースについても責任を持つわけです。
今度、日本で成功している営業のトップやマーケティングのトップが現地に入ります。この人たちは2年前、3年前は英語をまったく話せなかったのですが、今はもうひとりで行って、向こうのクライアントと普通に話ができる状態になっています。ですから、経営の考え方も、やり方も、社員の意識も大きく変わってきたということです。
――英語公用語化に踏み切ったときは、「英語は単なる手段じゃないか、そんなのは本質的ではない」という批判もありましたが、英語化によって、ゲームの戦い方が根本から変わった、と。
もうまったく変わりましたね。もうこれなしでは考えられないですね、本当に。だから、英語化していなかったら、ViberやVikiやKoboの買収も無理だったと思います。「彼らをマネジメントできない」ということになりかねませんから。それから相手側も、そういう会社に売ろうとは思わないけど、「まあ楽天だったらいいかな」というふうに思うということですよね。
――最近、ハーバードやスタンフォードといった大学からの採用も増えていると聞きました。
そうですね。ハーバード、イェール、スタンフォード。もともと少ないので、社内で20人も30人もいかないですが、けっこう入ってきています。
http://toyokeizai.net/articles/-/33821
優秀なエンジニアが増えたことで、ごちゃごちゃしてる不評の楽天のホームページの作りが少しでも改善されることを期待しています(^^;